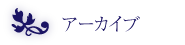勾留延長に入って今日で4日目。最初の勾留最後の頃(10日)には供述拒否に転じたとの報道があったので、捜査機関も新たに漏らせる情報はないだろう。マスコミは独自の取材活動をしているはずだが、その人間像や家族関係など、ほぼ何も出てこない。中で唯一、10年ほど前に撮られたという写真が出てきて、これがかなり衝撃的であった。ふくよかで、にこやかで、幸せそうな、どこにでもいる女性。殺人を犯したことでずっと悩んでいる中年女性を我々はどこかで想像していたのだが、見事に裏切られた形である。そう、彼女は自分が悪いことをしたとは露も思っていないはずなのだ。
大学時代に「精神病質」(ドイツのシュナイダー博士による10分類が知られている)を習った。「性格の著しい偏りのために自己が悩みまたは社会を悩ませるもの」がその定義であり、犯罪に絡むものはもちろん後者の「社会を悩ませるもの」である。それがアメリカ式の「人格障害」(=異常性格)となり、その響きが悪いというので、「パーソナリティ障害」に変わっているが、中身は同じである(精神保健福祉法は未だに精神病質としている)。精神科であまねく使われている「DSM-5 精神疾患の分類と診断の手引」(医学書院)は、パーソナリティ障害全般として、以下を挙げる(301頁)。
A. その人の属する文化から期待されるものより著しく偏った、内的体験および行動の持続的様式。この様式は以下のうち2つ(またはそれ以上)の領域に現れる。(1)認知(すなわち、自己、他者、および出来事を知覚し解釈する仕方) (2)感情性(すなわち、情動反応の範囲、強さ、不安定さ、および適切さ) (3) 対人関係機能 (4) 衝動の制御
B. その持続的様式は、柔軟性がなく、個人的および社会的状況の幅広い範囲に広がっている。C. その持続的様式は、臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている。D. その様式は、安定し、長時間続いており、その始まりは少なくとも青年期または成人期早期にまでさかのぼることができる。E. その持続的様式は、他の精神疾患の表れ、またはその結果ではうまく説明されない。F. その持続的様式は、物質(例:乱用薬物、医薬品)または他の医学的疾患(例:頭部外傷)の直接的な生理学的作用によるものではない。
パーソナリティ障害群はA群からC群のいくつかに分けられるが、混合型だったりどの型にも属さないタイプもある。これまで報道された事実を元にしての私の素人判断では、B群の一つ「自己愛性パーソナリティ障害」が近いのではと感じている。自分が重要であるという誇大な感覚があり、特権意識(特別有利な取り計らい、または自分が期待すれば相手が自動的に従うことを理由もなく期待する)があり、共感が欠如(他人の気持ちおよび欲求を認識しようとしない、またはそれを気づこうとしない)、他人に嫉妬する、等々の指標に合致すると思われるからである(なお、広く知られる「反社会性パーソナリティ障害」(=サイコバス)もB 群の一つである)。
彼女は私と同年代だが、この頃はまだバレンタインチョコを送ったり、ラブレターを送ったりすることは普通ではなかった。だが一見目立たない彼女は意中の彼(被害者の夫)にそれをしている。彼女自身は自分に大きな自信があり、自分がそうしたら相手は応じてくれると思っていたのではないか。しかし、そうはならなかったのに、なおも別の大学に行った彼を追いかけ、電車で1時間もかけて会いに行くこと数回、ついには近くの喫茶店に誘われてはっきりと断られて泣き出したという。その思い出は彼の記憶からは消えていたらしいのに、彼女の自尊心はひどく傷つけられ、以後決して消え去ることはなかったと思われる。報道によれば地元のエリートと結婚し、一女二男に恵まれた(長女は幼くして心臓の病気で亡くなった)のだから、普通であれば、それは青春時代の苦い思い出となるだけのことだったのだが。
1999年6月の再会時、どんな会話が交わされたのか。被害者夫に言わせれば、彼女から「結婚して家事も仕事も頑張っている」と(自慢げに)言われたのに対して、「それは良かった。頑張って」とか答えたくらいらしいが、およそ無関心な態度だと憤激したかもしれない。部活の同窓会だから、それぞれが皆の前で近況報告をしており、そこで11才下の妻と職場結婚し、子供も出来たと、とろけそうに幸せな顔で語ったであろうことは想像に難くない。今と違ってスマホの写真はないが、もしかしたら結婚式や一家の写真など持参していて、周りに見せたもしれない。結婚式によばれるなど被害者夫の近しい友人もその会に参加していたかもしれないことなど、警察は調べているだろう。自分たちより遙かに若くて美人の妻。本来であれば自分がそこにいるべき立場の女。嫉妬するのは普通だが、それを遙かに超えて、許せない、この女を抹殺して自分に苦痛を与えた男の幸せを永遠に奪ってやる、苦しめてやると考えたというのは、パーソナリティ障害の思考故であろう。普通の人の考えではどうやってもこんな動機は生まれない。いわゆる「了解不能な犯行」であり、その場合は本人の精神的な問題が考えられることになる。とはいえ、その5ヶ月間の思考、下見や凶器などの準備…それは本人にしか分からないことであり、だからこそ自白が待たれるのである。
黙秘権を行使して供述拒否に至ったのは、弁護人の示唆かもしれないが、そこは何とも分からない(弁護人は夫がつけたんですよね…?)。 誰もが納得できない動機であり犯行なのだから、素直に喋ったところで、裁判員が情状を酌んで求刑を少し下げてくれるとも思えない(裁判員制度になってから量刑はおおむね厳しくなった)。喋っても喋らなくても同じならば、喋らないでおこうと考えているのかもしれない。憎くてたまらない被害者夫の気持ちを軽くしてやる必要など露ほども感じていないのだ。無期懲役(今は無期拘禁刑)にはならず、最高刑で20年の拘禁刑。最後まで塀の中で過ごすことになるだろう。
なお、責任能力には問題がないが、検察は鑑定留置をすることになったようである。つまり20日の公判請求はない。