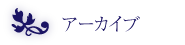佐藤智恵さんは以前、自民党前国会議員会の講師として来られ、お話を伺ったことがある。ハーバードでは学生たちの研修先として日本が一番人気なのだという。最も印象に残っているのが、新幹線が東京駅で折り返す際の車内清掃の話である。いかにこの会社では清掃団の統率が取れ、素早い臨戦態勢が確立されているか。数分の真剣勝負の根本にあるのが従業員の誇りだとは考えもしなかった。毎度当たり前のように接していて、不思議とも思わなかったが、日本で当たり前のことが世界では当たり前でないことはよくあることである。
ハーバードでの日本史教室(高校では日本史はほぼ教えられないとのこと)。登場教授には高名なエズラ・ヴォーゲルやジョセフ・ナイも含まれる。サムライや忠臣蔵が人気(源氏物語は不人気)というのは何となく分かる。忠義は何も武士道(ちなみに武士道という言葉は新渡戸稲造の造語であり、元から存在したものではないが)ひとりのものではなく、騎士道にも通じるからである。つまり人の生き方として美しいのだ。疑問に思ったのは原爆投下の正当化についての講義である(サンドラ・サッチャー教授)。トルーマンは朋友チャーチル同様、「本土上陸作戦よりも原爆投下のほうが戦争を早く終わらせることができる、結果的に犠牲者が少ない=人道的に正しい決断」として踏み切ったことになっている。これが正当化の理由の1つ目、「功利主義」である。2つ目は「戦争は地獄」(南北戦争時の北軍将軍による)、つまり戦争の罪は始めた人がすべて負うべきなので、真珠湾攻撃によって戦争を始めた日本に何をしても許されるということらしい。理由3つ目は(2つ目と似ているが)「スライディング・スケール」、真珠湾攻撃を仕掛けられたアメリカの正義は高いので、それに従って攻撃の度合いも高くてよい…。とにかく、リメンバーパールハーバー。戦争は宣戦布告をしさえすれば紛争の解決手段として許されるので、日本側が送った電報を何時間にもわたって放置していた日本大使館の怠慢が、終局的には原爆投下を招いたとも考えられるほどなのである。
トルーマンの原爆投下正当化論に対して、もちろん、アメリカにも反対論はある。『正しい戦争と不正な戦争』の著者マイケル・ウオルツアー教授いわく、戦争における最も重要なルールは「非戦闘員の保護」であるから、原爆投下は明らかにこれに違反している(←東京大空襲も当然に違反しているが、原爆投下は規模が違う)。また、「ダブル・エフェクト」の原則にも反している。これは、意図的に非戦闘員を攻撃することは人道的に許されない、戦闘員は非戦闘員の被害を最小限に食い止めるために最大限の努力をしなければならないということであり、連合国側は日本の軍部に対して「破壊的な威力を持つ新兵器を使う用意がある」と警告はしたが、広島や長崎の市民に対して(←ちなみに投下先候補として京都も上がっていたが、文化的な遺産を鑑みて回避された)避難する猶予を与えていない。かつ「比例性のルール」にも反している。これは過度の危害を与えることを禁じる原則であり、アメリカ政府が原爆が人間に与える危害の大きさを理解することなく使用し戦争を終結したのはこれに違反しているというのである。学生たちの意見は、原爆を正当化しないほうが多いが、中には少数ながら正当化する者もいるという。まあ、それはそうだろう。意見というのは様々にあるものだ。
しかし私がこの講義内容に不消化感を覚えるのは、大事な歴史的事実に触れられていないからである。当時ソ連は(日ソ不可侵条約を破り)日本侵攻を企図しており、そうなれば日本は降伏に踏み切らざるをえなかったであろうし、となると日本の戦後処理はアメリカが独自に進められるはずもなく、ソ連が主となって、あるいは少なくとも共同統治とならざるをえなかったと思われる。ドイツや朝鮮半島のように国は分裂させられていたであろう(天皇の存在があるからそう簡単にはいかないはずだが)。加えて、それ以前から開発を進めていた原爆が出来上がり、実際にその効力を試してみたかったというのが本当のところと思われるからである。当時すでにドイツはヒトラーが自殺し、国は降伏済みであって(1945年5月)、日本の降伏も時間の問題であった。実際水面下で進めようとしていたのに、アメリカが新兵器原爆を使用したいがために飲まなかったと、私が読んだいくつかの本には書いてあったし、私はそうであろうと理解している。もちろん白人相手には試さないので、有色人種だったことが大きい。そこにもってソ連の参戦情報が投下を急がせたのである。東京大空襲もそうだが、非戦闘民に対して無差別に爆弾(を超える殺傷能力を有する原爆)を投下するのは国際法違反の何ものでもない。広島への投下によって「参りました、降伏します」との日本側の対応を待つ暇もなく、3日後に長崎に投下したのは、先に原爆投下ありき、と考えないと辻褄が合わない。
須坂藩主堀直虎は、初めて聞く名前である(デビッド・ハウエル教授)。日本史は好きだし本も結構読んでいるつもりだが、全く聞いたことがなかった。幕末の、1万石の小大名(在信濃)であったが、英明であり、若年寄かつ外国総奉行に任じられる。1936年生まれ、1868年(未だ慶応4年時)、江戸城内で自死して果てた。図書館で『将軍慶喜を叱った男 堀直虎』(江宮隆之著)を借りて、読んだ。鳥羽・伏見の戦いに敗れて部下をほっぽり出して江戸に逃げ帰った慶喜がその詳細も知らせないまま、連日各藩の大名を集めて大評議を開いたのに対し、死を覚悟のうえ、万座の中、その責任を追及したというのである。仮にも現将軍に対してそんな大それたことをしたのは彼一人であろう。もっともどのように叱ったのかその内容、徹底抗戦を主張したのか朝廷への恭順を主張したのか、それさえ不明のままであるらしいのだが、海を越えて名前を知られているとは、すごいことである。堀自刃の少し前、その朋友で同い年の山内豊福(とよよし、土佐新田藩藩主)が朝廷派の土佐藩と旧幕派との板挟みの中、自刃して果てている(娘のために生きてくれと夫との心中を断られた妻も別の部屋で自刃し、娘2人が遺された)。
実はこの本を読んで初めて知ったのだが、最後まで幕府のために徹底抗戦した会津藩の初代藩主は松平正之。3代将軍家光の異母弟保科正之である(同母弟忠長は30歳になる前に自害に追い込まれている)。正室お江の方(淀君の妹)に遠慮した秀忠は正之の存在を隠し、信州高遠藩主の養子として育てられたが、その存在はやがて家光の知るところとなり、会津藩23万石への天封と松平家の名跡を与えられた。信頼を得て4代将軍家綱の烏帽子親となり、副将軍格となり、家光が亡くなる際に、「未来永劫、徳川家のために尽くしてくれ」と託された遺言「託狐の遺命」が、代々の会津藩と藩主とに受け継がれてきた掟であったという。それ故に幕府最後の難しい時に、会津藩主松平容保は京都守護職を引き受け、その弟で桑名藩主だった松平定敬は京都所司代を引き受けていたというのに、上記大評議の席に彼らはよばれなかったという。そのことも堀が指摘したというのは著者の読みである。
恥ずかしい話だが、二条城は家康が京都の別邸として建てたもので、本能寺の変のとき、信長の長男信忠が果てたのは二条御所であって、全く別物だということも初めて知った。やっぱり本を読まないと知識は入らない。ネットでは情報は入るが、それは断片的なものであり、知識はもちろん教養は、本を通してこそ入るものである。
東京は連日暑いのに、梅雨明け宣言が未だない。昨夕から記録的な雨で(記録がどんどん更新されていく)雷がひどく、気温が下がってよく眠れた。今日は30度を超えないようだ。年々温暖化が進み、クーラーに縁のなかったヨーロッパ各国もおしなべて猛暑である。だんだん住みにくくなっていて、少子化に歯止めといったって、こんな環境では子供も作れないよねと思ってしまう。