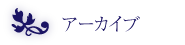カテゴリー
-
最近の投稿
アーカイブ
- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月
- 2007年3月
- 2007年2月
- 2007年1月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年9月
- 2006年8月
- 2006年7月
- 2006年6月
- 2006年5月
- 2006年4月
- 2006年3月
- 2006年2月
- 2006年1月
- 2005年12月
- 2005年11月
- 2005年10月
- 2005年9月
- 2005年8月
- 2005年7月
- 2005年6月
- 2005年5月
- 2005年4月
- 2005年3月
- 2005年2月
- 2005年1月
- 2004年12月
『離婚後の子供とお金のこと、どう整理すればいいでしょうか。』
カテゴリー: 執筆
『離婚後の子供とお金のこと、どう整理すればいいでしょうか。』 はコメントを受け付けていません
自民党の歴史的圧勝に終わった総選挙に思うこと
予想通りだった。というか予想を遙かに超えた。自民党316議席!衆院465議席の過半数233議席どころか、絶対安定多数261議席どころか、3分の2の310議席をさえ上回ったのである。ちなみに小選挙区ですべて勝ったことで比例名簿登載者が出払ってしまった14議席は中道などに割り振られたため、本来であれば?330議席だったのである。316議席に与党の維新を足せば354議席!参院で否決されても(今のところ参院は与党で過半数に達しない)衆院で再可決すればすべての法案が通過することになる。
中曽根総理のときに300議席に達したことはあるが、今回はそれをさらに、はるかに上回り、歴史的圧勝であることは間違いない。勝因についてあれこれ言われていて、たしかに初めての女性総理である高市さんの魅力によるところも大きいが、それを拡散させたネットの力が、新聞やテレビといったいわゆるオールドメディアを完全に凌駕したのがこの選挙戦だったと感じる。若者がタレントを応援しているのと同じで、押し活というらしい。選挙が変わったのである。
何より大きいのは、前にも書いたが、反自民の受け皿になるべき野党第一党が自滅したことである。結果、選挙前148もあった立憲議席はなんと21に!うち小選挙区当選者はわずかに7人。ただの大敗ではなく壊滅的大敗である。最初半減と言われていたが、日に日に少なくなって50を切ると言われだし、実際はなんとその半分を切ったのである。当選率たるや、わずかに14%!小沢、安住、岡田、枝野、玄葉、海江田といった重鎮が軒並み敗戦。野田だけはなんとか生き残ったが、当然ながら代表を辞任した。中道勢力は、比例上位を独占した公明党が選挙前の24からちゃっかり28議席に増やし(小選挙区4つから撤退したというのに)、立憲と併せて49議席である。巨大与党に対して野党第一党のなんとささやかなことか。この際解体をして元の党に戻るのかと思いきや、数あわせ故なのか、このままでいき、13日に新しい代表を選ぶのだという。公明党からではなく立憲から。誰かなり手がいるのだろうかと思うけれど、候補者の名前はすでに挙がっているようである。
野田さんは2012年11月、民主党政権3人目の首相として解散に踏み切り、12月の総選挙で議席数を現有230から57に落とした張本人である。その当選率は25%で、今回よりはマシだったのだろうが、これはたまたまではなく、やはり野田さんには壊し屋となる必然的なものがあるのだろう。この高市を首相に選ぶのか、野田さんや齊藤さん、あるいは他の人を選ぶのか、と高市さんはあまりに率直に語りかけたが、どうやらそれが自民党への投票行動に繋がったとの指摘は大きい。冴えないおじさんたちに首相になってもらって、トランプやら世界の大物と対峙させられないよねと、素直に感じた人が多かったはずだからである。
二大政党というか、替わりうる野党の政党の存在は必要だと思う。見ていると、与党の批判ばかり、どうでもいいようなことの揚げ足取りが多すぎて、これでは国民を辟易させるだけである。自分たちはこの国をどうしたいのか、ビジョンを示せなければ、政権選択選挙とはなりえない。今回彼らは政権選択などとは一言も言わなかったが、もともとそのつもりがないのである。選挙に勝って議員でいることが目標なのだろうかとさえ思う。ネット時代の下、一挙手一投足が瞬時にリアルに拡散されている。ちびっ子ギャング安住さんが静岡の候補者の選挙応援に行って、「新幹線の中で脚を組んでクリームパンを食べていたら、生意気だと投稿された。ひどい国だ」とつまらないことを、それこそ生意気に喋っていた。候補者も呆れただろうけれど、人前で食事をするときに脚を組むなんて、そもそも行儀が悪すぎる。以前からなんでこんな人を地元民は選ぶのだろうと思っていたけれど、今回、自民党候補に4万5000票もの大差をつけられて敗れた。敗因を自らのせいにせずに、ネットでの誹謗中傷のせいにするなんて、情けなさすぎる。彼を含めてもう戻ってはこれない人が多いと思われる。小選挙区でもこれだけ、新陳代謝が働くことがあるのである。
さて自民党。2年前の総選挙で敗れた元職もいるけれど、新人も100人近くはいるのではないか。なにせ今回全小選挙区に候補を立てて、自民党というだけで当選した人も多いのである(比例復活組も含めるとほとんどが当選しており、完全な落選者は数えるほどしかいない)。以前の小泉チルドレン、安倍チルドレンの時を思い起こし、彼らを教育・監督していかなければならない。かつては派閥がその役割をかなり担っていたが、今派閥は麻生さんの所を除いて消滅してしまった。会社の新人教育のように、一から教えなければならないことが多いと思われる。個々人がやはりそれぞれ能力と適性を持たなければ、政党も弱いものになってしまう。そして、絶対多数にあぐらをかくことなく、どうか謙虚に、国政を進めていってほしいと願っている。
カテゴリー: 最近思うこと
自民党の歴史的圧勝に終わった総選挙に思うこと はコメントを受け付けていません
ノルウェー王室の大スキャンダルに思うこと
私は実は物心ついた頃からお姫様が大好きだった。その昔英字新聞を購読していたとき、結構王室関連記事はあり、内容も詳しかったので、わくわくしながら読んだものだ。王室の代表は英国だが、スペイン、ベルギー、オランダ、デンマーク、スウェーデン、ノルウェーの王室も知られる。小さな国ではルクセンブルク、モナコ。別の地域にまで広げると、ヨルダン、モロッコ、タイ、ブータン、ブルネイ…。王室の華は女性である。美しくファッショナブルな女王、王妃と王女。女優ほどの美貌やスタイルは望めなくても、国の文化歴史を背負った威厳や気品は女優の比ではない。
デンマーク王室は世界最古の王室とも言われ、「ハムレット」のモデルはデンマークである。代々王家出身者ないし貴族と縁組みしていたが、現国王の妻メアリー王妃はオーストラリアの僻地タスマニア出身で、当時王太子だった国王とはシドニーオリンピックの際にたまたま?知り合ったという。彼女はタスマニア大学卒で、父は大学教授である。もちろん平民だが、非常にファッショナブルで評判が良い。国王の弟ヨアキムは初めて中国系の女性(ビジネスウーマン)と結婚して大きな話題をよび(英字新聞一面にわたる記事だった)、男児2人を設けたが、その後離婚。ヨアキムはパリ出身のマリーと再婚してさらに1男1女を設けたものの、王室のスリム化号令の下、今では一家で王籍を無くしている。現国王には2男2女がおり、長男が後継となる。
ノルウェーは独立して100年少し、デンマークから王家が来て、現ハラール国王は在位34年、88歳とヨーロッパ王室の最長老である。その妃ソニアは同王室初の平民出身で、2人の関係は9年間もの間秘密にされていたという。2人とも未だに国民の敬愛を集めている。子供は2人。長女は小説家と結婚して3女を設けたが離婚(その後夫は自殺)、一昨年だか、黒人の自称霊媒師と反対を押し切って再婚し、大きなニュースになった。弟ホーコンが王太子(皇室ではないので皇太子ではなく王太子とよぶのが正しいと思う)で今52歳。背が高くなかなハンサムで、善良そうな顔をしている。問題はその妃、メッテ・マリットである!(同い年)。
彼女は学歴もキャリアもなく、オスロ大学でウェイトレスをしているときに王太子と知り合い、同棲を始めた(王太子がそんなに軽薄でよいのか!?)。彼女はシングルマザーで、息子マリウスの父親は薬物犯罪により刑務所入所中。彼女自身麻薬をやり、ひどく荒れた生活を送っていた過去を持つ。当然ながら国王夫妻ら周りは大反対したが、世間知らずの王太子は押し切った(結婚を認めてくれなければ王室を離脱するとまで言ったらしい)。普通の女であれば、自分では身分が違いすぎる、私には務まらないと身を引くはずだが、そんなことはまるでなかった。それだけ王太子を愛していたのか、と言うと、今回のスキャンダルからも推察されるように、そうではなく、身分不相応にもただ豊かな暮らしがしたかったのだと思わざるを得ない。要するに世間知らずのボンボンが百戦錬磨のどうしようもない女に引っかかったのである。メーガンに引っかかったヘンリー然り、男女は逆さまだが我が皇室にもいたなあ。まだ次男だから良かったのであって、これが世継ぎとなれば目も当てられない。
彼女が国民の前で涙ながらに過去を悔いて共感を勝ち得たシーンは私も見たが、私もすっかり騙されていた。国王らは、嫁のコミュニケーション力が素晴らしいと褒め称えていた。心の中では皆チョロいもんだと舌を出していたのだろう。連れ子マリウスは4歳で王室に入れてもらい、王太子の娘・息子が生まれた後も、分け隔てなく可愛がられていた。色白金髪のとても可愛い子であるリトルマリウスは国民の注視の的だったのだが、20歳で王室を出て民間人となって以降、どこでどう間違えたのか、今では全身に入れ墨を入れ、大学も続かず職業も続かず、2年程前から警察沙汰でのみ世間を賑わすようになった。逮捕歴、実に4回。レイプ4件を筆頭に、家庭内暴力、器物損壊、証人威迫、大量の薬物運搬等々、今月オスロ地裁で始まった刑事裁判の公訴事実は全部で38件に上るという。今、29歳。マリウスはスピード違反などの軽罪のみを認め、あとはすべて否認。被害者らは公判によばれることになるだろう。オスロには世界中から報道陣が集まっているが、マリウスに昔の面影は全くなく、すでに完全な悪人面である。父親が前科者だった血はやはり争えないものである。今回知ったが、母親の父親(祖父)にも前科があるという。よくぞまあ、そんな女との結婚を許したものである。一般家庭でも許さないのに、まして国家と国民を象徴する王室なのである。
それに追い打ちを掛けるように、問題の王妃そのものの、恐ろしすぎるスキャンダルが噴出した。アメリカの小児性愛者で犯罪者、大富豪のエプスタインとの親しすぎる交流である。米国司法省が一部黒塗りとはいえこの度開示した2人のメールのやり取りは1000通にも上る。2011年~14年。ほぼ毎日やり取りをしていた計算だ。エプスタインと交流して自らも買春など犯罪に関与したと言われる英国のアンドリュー王子(チャールズ国王のすぐ下の弟)は様々な証拠が提示されたことにより、王籍を剥奪された。エプスタインは2008年には小児性愛・人身売買などの犯罪で有罪・拘禁刑になり、そのことは世界中に報道されていたのに、王妃は付き合ったのである。2019年にエプスタインが勾留中に自殺したが(66歳。口封じに殺害されたとも言われる)、王妃はマスコミに対して、「どんな人か知らなかった。検索しなかった」と弁解していたのである。いつも、この人は完全に舐めている。性格が悪く、何より頭が悪い証左である。
ところが、今回詳細なメールが公開されたのである! この中で彼女は、「検索したら、あなたあまり評判が良くないみたいね(笑)」と言っているのだ。忌むべき性犯罪者だと分かっても平気、どころか親しく付き合うというのは、普通の人の神経ではとうてい計り知れない。そんなのが母親だから息子が性犯罪を犯すことに抵抗がないというのはよく分かる理である。エプスタインを「とても魅力的」と言い、sweetheart (恋人)と呼びかけ、互いに会って買い物に行ったりしている。フロリダの豪邸(性犯罪が行われた場所)にも招かれて宿泊し写真を撮られている。王太子は、妻を放ったらかしで監視も監督もしていないのである。宮廷も組織としても体をなしていない。マリウスはもちろんだが、このスキャンダルは王妃自身に関わることだけに、限りなく重大であり、ノルウェーは毎日このニュースで持ちきりだという。それはそうだろう。日本の皇室でこんなことが起こったらと考えるだけで恐ろしい。
とにかく彼女は底抜けに軽くて、もとより知性のかけらもない。15歳の息子(マリウス)の壁紙(パソコンの背景?)を裸の女性2人がサーフィンをしている写真にするのはどう思う?とエプスタインに聞き、「それは本人が決めることだ」「いいえ、我が家ではママが決めるのよ」! ただでさえ遺伝子が良くない息子がこんな環境に育てば、ますます野放図になるだろう。バリバリの性犯罪者になった息子に性犯罪者と親しく楽しく交遊していた母親。笑えない一致である。「ここで私は退屈で死にそうよ」と国民が呆れ果てる言葉が続き、おまけに「ルクセンブルク王太子の結婚式に行ったけれど、本当に退屈だった」と王室外交を無にする言葉も呈する。心底、誰であれ付き合いを避けたい、とんでもない人なのだ。こんな女の本質も見抜けず、20年以上連れ添ってきた夫は一体どんな人間だろうか。彼に普通の良識があれば、 こんな女を妻にすることはなく、王室の危機を招くこうした事態になりようがなかったのだ。さすがに後悔しているのだろうか、それともただ運が悪かったと思っているのだろうか。
こんな女を未来の王妃に仰ぎたいと思う人は、少なくて当然である(20%もあってびっくりした)。この際王太子は離婚するべきだ、しないのであれば王位を離脱してほしいと、国民は思うだろう。次の王位は長女のアレクサンドラ王女である。22歳。一見気品のある美人であり、今オーストラリアに留学中だが、彼女の母親がこういう人であり、彼女の半分はその遺伝によると考えると、本当のところはどんな人であるのか、全く分からない。母親を王妃にすることなく娘が現国王からすぐに王位を継いで女王になるとしても、母親の存在を消すことはできない。異母兄が重罪犯罪者であることも消せない。どこの王室であれ、彼女との交際は身構えるであろう。であればいっそ、王室を廃止して、共和制にするという選択肢も国民にはある(フィンランドには王室はない)。とんでもない結婚によってもたらされた、世界中の知る恥ずかしいスキャンダルによってノルウェー国民が陥っている苦境を思うと、本当に気の毒で同情を禁じ得ない。国民には何の罪も責任もないのだ。小室騒動はだいぶ前になるが、これと比べると、まだずいぶん軽い打撃だったと思われてしまうくらいだ。
カテゴリー: 最近思うこと
ノルウェー王室の大スキャンダルに思うこと はコメントを受け付けていません
選挙戦、真っ只中…
衆院選は12日しかないので(参院選は17日)、あっという間に後半戦に突入している。情勢調査によると、自民党が圧倒的に勝つらしい。前回と今回、自民党のどこが変わったかといえば、ぶっちゃけた話、首相が石破さんから高市さんに変わっただけである。2人はリベラルと保守で立ち位置が明確に違うが、そういう政策や思想の違いではなく、何を言っているのか分からない陰気な石破さんに比べて、分かりやすい言葉で明瞭に述べる高市さんが好感されているというシンプルな理由であるらしい。特に若い層にサナエファンが非常に多いというが、私などはよく分からず周りに聞くと、ネット民にしか分からないという。自民党が233議席を獲得できれば単独過半数を超えるが、それ以上の議席数にもなるとの読みがあり(しかし、そうした無党派層は実際に投票に行くのだろうか…)、維新と併せて300議席すらありえるという。もちろんまだ分からないが、もしそうなれば、高市さんのいわばギャンブル勝ちである。
公明党は高市さんを嫌って昨年10月与党を離脱したが、今回の選挙前、突然のように立憲民主党と合流して新党を結成した。その名も「中道改革連合(=中革連)」。過激派華やかなりし頃に検事であった私としては、中核とか革マルとかのイメージに繋がり、古いし、なんとセンスが悪いのだろうと素直に思う。そもそも立憲は安全保障法案と原発再稼働に反対していたのに、公明党の組織票欲しさに迎合してどちらも賛成にしてしまった。これで多くの議員が離脱すると思っていたが、原口さんなどごく一部の議員以外は新党に加わったので、かえってびっくりした。思想信条ないし政策は議員の命であると思うが、議席を得るためには良心を捨ててもなんら恥じることはないらしい。そもそも彼らにとってそんなことはどうでもよかったのかもしれないし、とにかく議席を得ないことには何も始まらないのだが、これではコアの立憲支持者は離れていくであろう。本来野党たるもの、既存の組織票に頼るのではなく、無党派層・浮動票をターゲットにして支持者・票を増やすべきである。その層が与党自民党に流れているのでは落ち目は当然である。
この新党は今回の総選挙用のものにすぎず、参院では元のままだし、地方ではもちろんそうである。かつて希望の党や新進党といった新党で大失敗した記憶は未だ鮮やかであり、彼らは、俄作りの新党がうまくいかないことも考慮に入れて、戻れる党を残したのであろう。新党の名前は未だ浸透していない。公明党という歴史ある党名があり、26年間も自民党との連立を組んで与党の立場にいたのに、自民党との連立を解消したうえ、長らく敵だった立憲とくっついたことについて、納得している学会員はどれほどいるのだろうか。長く公明党と書いていた人が俄に中道と書くのは、ことに高齢者には難しいはずである。選挙区は個人名なので党名は関係ないかもしれないが、そもそも長く自民党を応援していたのに、急に立憲議員に投票しろ、その当選のために運動してくれと言われて、応じるのだろうか。自民党から学会票が減る分中道が増えるといった単純な計算式から、自民党大負けと試算していた人たちが当初かなりの数いた。計算上はたしかにそうだろうが、いくら宗教政党で上からの指示が絶対とはいえ、池田大作氏はもういないし、自らの素直な感情ではやはり立憲の応援には動きたくないのではないか。
比例区では無効票が続出するだろうと思う。「立憲」や「公明」は無効である。もし「民主党」と書けば、国民民主党に行くらしい(自民党は自由民主党なので、按分比例で自民党に行ってもよいようなものだが(笑))。公明党は現有4つの小選挙区から撤退し、比例区11ブロックのすべて上位につけたので万全であり、28名は当選確実であるらしい(現有議席数24名より上回る)。片や旧立憲議員は比例区順位が後位なので、小選挙区で当選しないかぎり、比例復活はまず望めないはずだ。このマジックは公明党に救ってもらう立場としての立憲が、おそらく野田・安住・馬淵といった執行部だけで飲んだものであり、ほとんどの議員は公示で知らされて唖然としたのだろうと思う。今は恨みつらみも言ってはおれないが、多数の議席を失った選挙後爆発するはずだ。旧立憲議員は解散前150議席もあったのに(反石破の受け皿となったために、信じられないほど多かった)、今回は50名も当選しないだろうとも言われている。野田さんはさすがに選挙に強いが、安住・枝野・岡田などの重鎮ですら危ないとすら言われているのだ。
8日午後8時には大勢は判明する。野田さんは即刻代表を辞任すると思われるが、とすれば新党の代表は誰になるのだろうか。今は暫定的に両党の代表が共同代表という立場を取っているだけで、代表を選ぶ手続きも決められていないのである。特別国会での首班指名はどうするのだろうか。国民民主党は50議席を狙っていたが、現有の30議席程度であるらしく、立憲の残党と組んでの野党新党を立ち上げるにしても弱小すぎる。こんなことなら高市さんの呼びかけに応じて与党連立に加わっておけばよかったと後悔しているかもしれないが、今更悔やんでももう遅い。大量議席を得た与党から当てにされることはない。とにかく優柔不断で決断が遅すぎるのだ。その点、公明党が離脱した後すぐに維新と組み、麻生さんや幹事長にも内密にしたまま一見無謀と思える解散に打って出た高市さんは、毀誉褒貶はあるにしろ、とにかく凄い勝負師である。もっとも総選挙はまだであり、自民党にそこまで大勝させてはいけないと考える選挙民もいるだろうし、当日の大雪情報もあり、投票率次第では(期日前の投票率は今のところ前回より少ないらしい)ことに激戦区の結果は当然ながら変わり、予想が当たるとはまだ言えないのであるが。
カテゴリー: 最近思うこと
選挙戦、真っ只中… はコメントを受け付けていません
最近のいくつかのニュースについて思うこと
少し前になるが、この1月12日、前橋市長だった小川晶氏が再選した。6万2000票は前回の初市長選で取得した票数より多かったとのこと。対抗馬として自民党が立てた丸山彬弁護士は5万2000票であり、善戦はしたと評価できる。千葉出身で司法修習の実務修習地がたまたま前橋だった小川氏とは違い、丸山氏は地元の名門前橋高校出身で、親子3代にわたって前橋で弁護士をしているという。まだ40歳で政治経験はないものの、いくらなんでも市民は小川氏を再選させたりはすまいと思っていた。小川氏再選の背景には、山本一太群馬県知事(元自民党参院議員で、私もよく知っている)が丸山氏を強く支持し、小川氏を連日Xなどで執拗に叩いたことが市民の同情ないし反感を買い、小川氏有利に働いたと聞く。
彼女は独身なのだから、男とラブホに行って何が悪い、とか言う人もいる。たしかに私人としての立場であればそうだろうが、上司と部下との関係なのだ。もしこれが逆に、市長が男、部下が女であれば明らかなパワハラセクハラとして直ちに失脚ものであり、再選など望むべくもなかったはずである。男女平等といいながら、そこはまだまだ旧態依然の感覚の人が多いように感じる。小川氏は相談していただけで男女関係はなかったとの苦しい言い訳に終始していたが、男女がラブホに行くきっかけもそこですることも、ただ1つである。苦しい言い訳を信じた者はおるまい。そもそもラブホに公用車に乗り付けるなど、立場を弁えないにも程がある。もし密会をするのであれば、他にいくらでも然るべき場所があるだろう。しかも、相手の男には降格に続いて、6ヶ月の職務停止の懲戒処分をしたことにより、彼は昨年末で自主退職をした。婿養子で子供はまだ高校生と言われ、相手及びその家族がこの一件で壊滅的打撃を受けたことに鑑みれば、自らもせめて綺麗に引くべきであった。それを、私は前橋を愛している、まだ前橋のためにやり残したことがあると言い張る神経はどう形容したらよいのか。政治家としては有能だと思う人がいるのかもしれないが、政治家は人間であり、基礎になる人間性がずれて、常識を欠いていれば政治家云々の話ではないはずだ。
1月21日、安倍氏襲撃の山上被告に対して無期懲役判決が言い渡された。私の予想通りであった。そもそも本件は政治テロだし、銃器を使っているので(他も巻き込むおそれが非常に高い)、被害者は一人であるものの求刑相場は死刑であった。それを、統一教会から多大の被害を受けたことなど、公判に顕れた彼にとって有利なすべての情状を考慮したうえで、検察は求刑を無期懲役に落としたのである(もちろん最高検と評議済みである)。その事情を検察も論告求刑時にしつこいくらいに述べていたので、裁判員評議の際、これらを情状酌量してさらに下げようとの意見はあまり出なかったのではないかと思われる。もし本件犯行が、直接の加害者である統一教会関係者ないしは母親に向けられていたのであれば、求刑・判決は有期懲役に留まったが、安倍氏は何らかの関係はあったにしろ、加害者の位置づけにはない。これによって統一教会の悪辣さが明るみになって良かったと言う人は周りにも結構いるがそれは結果論であり、安倍氏が殺害されるべき正当な動機とはなりえない。被告は出所後は大学に行って人生をやり直したい、と言っていると報じられたことがあり、えっ、まさか短い懲役で出てこれると思っているの?と驚いたが、判決後は納得しているとの報道があり、いささかほっとしている。弁護士らは控訴するだろうが、おそらく覆ることはないだろう(新たに出てくる証拠もないはずだ)。無期懲役の場合の仮釈放は、認められるまでの収容期間がどんどん長くなり、30年近くを要するようになっている。
明日総選挙公示。食品の消費税を当面無くす旨各党が言い出しているが、それによって失われる財源はどこから捻出するのか。大体、簡単に言うが、現場の会計処理は大変なことになると思われる。一時金を配るとか、赤字国債はまだまだ余裕があるのでどんどん出せとか、適当なことを言っている党首などもいて、聞いてられないとテレビを消した。無学など素人が国会議員になっていいものだろうか。こんな無責任な人たちに企業の経営をさせたら、すぐに潰れるだろう。弁護士業のような形態ですら要は、収入支出のバランスを考えないと成り立たないのである。何をどうしても2月8日夜には大勢が判明する。どこに入れてもダメだよなあと思っている国民も多いと思うが、棄権をして国がよくなるわけでもないので、是非とも投票には行ってほしいと思っている。
さて、TACOとは何かご存じだろうか。Trump Always Chikens Out. の頭文字を綴った造語で、高関税を課すぞと脅しておいて、相手の様子を見てすぐに引っ込めるというトランプの態度を揶揄したものである。グリーンランドを巡り、トランプのあまりに強圧的な態度に憤慨したNATO各国が連帯して反旗を翻したため、さすがにトーンが落ちてきたようである。国際報道では、ミネソタ州ミネアポリスで、連邦移民局が不法移民を閉め出そうと強権的行動に出、アメリカ国籍の女性運転手に発砲して殺害した事件を巡り、マイナス20度の極寒の中、反政府デモが大きなうねりとなっていることが連日報道されている。アメリカの市民はその歴史上、個人が巨大な権力に潰されることに非常に鋭敏である。やはりそこは独裁国家や共産主義国家とは違う、民主主義国家なのだと思わされる。
カテゴリー: 最近思うこと
最近のいくつかのニュースについて思うこと はコメントを受け付けていません