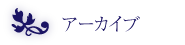前回5日(金)にブログを書いた後に事態は急転し、石破さんが週末に総裁を辞任したため、初めての臨時総裁選要求はなくなり、普通の総裁選が行われることになった。前回は9人の候補だったが、報道によると石破さんを除く8人のうち5人が立候補する予定とのこと。そして総裁選は10月4日。本当に、1年で同じことが繰り返される。
日本の首相はほぼ1年毎に替わっている。任期の決まった大統領制とは違い議院内閣制だからとはいっても、イギリスでもまさかこれほどは変わらない。国際会議に出ても、これでは名前も顔も覚えてもらえない。顧みて、中曽根さんが各国首脳陣の真ん中に堂々と立ち、背も高くしゅっとしていて、日本人として大変誇らしかったのを思い出す。ずいぶん昔のことだと思って調べたら、昭和57年11月から同62年11月まで、通算1806日である。レーガン大統領とのロン・ヤス関係も任期の長さあればこそである。中曽根さんは俳句も俳画もされる趣味人で、私が参院議員のとき、同じ派閥の懇親会で、余興にフランス語で「枯れ葉」を唱われたのをよく覚えている。
候補者があまりに小粒だと前にも書いた。ずっと思っている。これぞ政治家という人をついぞ見かけなくなった。政治家に限らず、どの世界でもこれぞという人を見なくなったのは、やはり教育のせいだろうと思っている。厚い本をじっくり読むのではなく、軽い実用本を、それどころかスマホで断片的な知識を仕入れるようになったのでは、思考の厚味など出来ようはずもない。これに加えて、政治の場合は、選挙制度の変化が大きいと思われる。中選挙区制から小選挙区制に変わって、30年。中選挙区制では候補者の基盤は党ではなく派閥であり、派閥同士が競い合っていた。派閥の機能はまさに総理総裁候補を出すことにあったが、いつかしらそれが崩れて、これぞトップという候補者を出すことがなくなった。ついに最近では派閥が解消され(残っているのは麻生派のみ)、総裁を出すバックアップ機能が確固たる集団ではなくなった。個人の繋がりだけでは弱いと思うが、5人の候補者はそれぞれどういう組織・集団に支えられるのであろうか。
そもそも小選挙区制導入の理由は、アメリカやイギリスに倣って二大政党制にしようということであったはずだ。ところが、二大政党どころか、様々な党が乱立する一方で、選挙区で一人しか当選しない小選挙区制度では死票が増えるばかりである。ドイツでは小党が乱立した隙を縫うようにナチスが勢力を伸ばした歴史的事実を反省し、得票数が5%以下の党には議席を与えないという5%ルールが適用されているとのことである(これを適用すれば、日本でも議席を与えられない党がいくつか存在する)。死に票を増やさず民意を取り入れるためには、中選挙区連記制(複数名を書く)が望ましいとの議論をよく耳にするようになった。最初聞いたときには、そんな面倒な選択を選挙民が出来るわけないでしょ、馬鹿馬鹿しいと思ったりしたものだが、さりとて、このままではいけないこともまた事実だろうと思うのだ。
かつての中選挙区制では自民党議員も何人か選挙に出て(派閥をバックに競うことになる)、名前は一人を書くだけだが、無能だと思われれば世襲議員でも落選して新陳代謝が図られていたものだ。小選挙区になって以降、議員が亡くなればたいていその遺族が世襲し(形は公募にするにせよ)、自民党支持者は不満があってもその名前を書かざるをえないし、それが嫌であれば投票自体を棄権して投票率が下がる、ということになる。とにかく選択肢が少なすぎるのである。自民党に入れたいけれどこの人しかいないし、さりとて他の政党の候補者を書くわけにもいかないし…と選挙の度に悩むことになる。選挙制度の改革は折に触れて言われ続けているが、本当に考えないといけない時期にきていると切に思うものである。