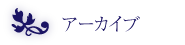お芝居を見るのは久しぶり。昔読んだ原作は短編だが、とても面白かった。旦那が急に亡くなって後の本妻、妾、妹を巡るバトルの話である。配役は、本妻大竹しのぶ、妾キムラ緑子、妹渡辺えり。どれも非常に巧い役者なので、楽しみにしていた。
結論から言うと、非常によく出来た脚本と舞台装置であり、演技はどの人も素晴らしかった。ただ、時に「演技の天才」とも言われる大竹しのぶの声量のなさにはいささか驚いた。新橋演舞場のほぼ真ん中の席でこれだったら、後方や2・3階席には聞こえただろうか。片や、キムラも渡辺も、よく通る声を腹から出しているので、聞き苦しさなどまるでない。そうか、2人とも劇団出身だ。発声の基礎がよく出来ているのは宝塚出身者も同じである。
3人はいずれも60歳の設定だが「婆」、つまり当時は立派な老人であった。どの人にも子供がいない。夫の死後妾と妹が本妻宅に押し掛けてきて、バトルが繰り広げられ、しかし結局本妻も1人になるのは寂しいからと折れて、奇妙な同居が続く。20年後、80歳になった3人は同じ所で同じように暮らしている‥。この小説は、老人の将来・孤独を確実に予見したものであったろうし、また疑似家族を描いているという点で非常に新しかったと思われる。かつて亡夫の忠実な部下であった重介(段田安則:好演)は、故郷の鳥取に帰り娘の嫁ぎ先で暮らすと帰ったものの邪険にされて家を出、結局この3人と一緒に住んでいるのであるから、本当の家族よりも近しいのである。
しかし、見ながら、いくつかの疑問が出てくる。一番は「この家の名義は?」 昭和55年の民法改正以前は、夫婦に子供がない場合、法定相続分は妻3分の2対妹3分の1であった(今は妻4分の3対妹4分の1)。つまり、妹が遺産分割協議書にサインをしない限り、妻は家を自らの単独名義にはできない。しかるに、妹は「この家は私のものだ。唯一血を分けた私のものだ」と折に触れて叫んでいる! つまり、名義は亡夫のままであろう。それでも固定資産税は払っていけばよいだけだが、そのままでは売却はできない。であるので、回りはすべてマンションになっているのに、古くなる一方の家屋に住み続けているのだろうか? 最初の頃、本妻が妹を厄介払いにしようと老人ホーム入所契約を勝手に結んできたのだが、ありえない! 成年後見はもちろん当時なかったし、今でも、妹には意思能力があるのだから勝手に成年後見には付せないし、従って勝手にそんな契約を結ぶことはできない。
ところで、昨日のブログ(その2)の真相。再捜査の公表について、FBIのコミー長官は、司法省から大統領選前を理由に止められたのだが、内部の反クリントン派がトランプ氏支持のジュリアーニ元ニューヨーク市長に、捜査情報を提供。同氏が再捜査発表の2日前に「近々ヒラリーに関して爆弾が破裂する」旨表明した(これは知っていた)ため、結局長官は公表せざるをえなくなったということであるらしい。捜査はすべからく守秘義務を伴う。FBI職員の違反は明らかだし、捜査という最大級の公務と個人の政治嗜好が絡み合うなど日本では考えられないことである。