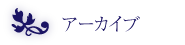予想通りだった。というか予想を遙かに超えた。自民党316議席!衆院465議席の過半数233議席どころか、絶対安定多数261議席どころか、3分の2の310議席をさえ上回ったのである。ちなみに小選挙区ですべて勝ったことで比例名簿登載者が出払ってしまった14議席は中道などに割り振られたため、本来であれば?330議席だったのである。316議席に与党の維新を足せば354議席!参院で否決されても(今のところ参院は与党で過半数に達しない)衆院で再可決すればすべての法案が通過することになる。
中曽根総理のときに300議席に達したことはあるが、今回はそれをさらに、はるかに上回り、歴史的圧勝であることは間違いない。勝因についてあれこれ言われていて、たしかに初めての女性総理である高市さんの魅力によるところも大きいが、それを拡散させたネットの力が、新聞やテレビといったいわゆるオールドメディアを完全に凌駕したのがこの選挙戦だったと感じる。若者がタレントを応援しているのと同じで、押し活というらしい。選挙が変わったのである。
何より大きいのは、前にも書いたが、反自民の受け皿になるべき野党第一党が自滅したことである。結果、選挙前148もあった立憲議席はなんと21に!うち小選挙区当選者はわずかに7人。ただの大敗ではなく壊滅的大敗である。最初半減と言われていたが、日に日に少なくなって50を切ると言われだし、実際はなんとその半分を切ったのである。当選率たるや、わずかに14%!小沢、安住、岡田、枝野、玄葉、海江田といった重鎮が軒並み敗戦。野田だけはなんとか生き残ったが、当然ながら代表を辞任した。中道勢力は、比例上位を独占した公明党が選挙前の24からちゃっかり28議席に増やし(小選挙区4つから撤退したというのに)、立憲と併せて49議席である。巨大与党に対して野党第一党のなんとささやかなことか。この際解体をして元の党に戻るのかと思いきや、数あわせ故なのか、このままでいき、13日に新しい代表を選ぶのだという。公明党からではなく立憲から。誰かなり手がいるのだろうかと思うけれど、候補者の名前はすでに挙がっているようである。
野田さんは2012年11月、民主党政権3人目の首相として解散に踏み切り、12月の総選挙で議席数を現有230から57に落とした張本人である。その当選率は25%で、今回よりはマシだったのだろうが、これはたまたまではなく、やはり野田さんには壊し屋となる必然的なものがあるのだろう。この高市を首相に選ぶのか、野田さんや齊藤さん、あるいは他の人を選ぶのか、と高市さんはあまりに率直に語りかけたが、どうやらそれが自民党への投票行動に繋がったとの指摘は大きい。冴えないおじさんたちに首相になってもらって、トランプやら世界の大物と対峙させられないよねと、素直に感じた人が多かったはずだからである。
二大政党というか、替わりうる野党の政党の存在は必要だと思う。見ていると、与党の批判ばかり、どうでもいいようなことの揚げ足取りが多すぎて、これでは国民を辟易させるだけである。自分たちはこの国をどうしたいのか、ビジョンを示せなければ、政権選択選挙とはなりえない。今回彼らは政権選択などとは一言も言わなかったが、もともとそのつもりがないのである。選挙に勝って議員でいることが目標なのだろうかとさえ思う。ネット時代の下、一挙手一投足が瞬時にリアルに拡散されている。ちびっ子ギャング安住さんが静岡の候補者の選挙応援に行って、「新幹線の中で脚を組んでクリームパンを食べていたら、生意気だと投稿された。ひどい国だ」とつまらないことを、それこそ生意気に喋っていた。候補者も呆れただろうけれど、人前で食事をするときに脚を組むなんて、そもそも行儀が悪すぎる。以前からなんでこんな人を地元民は選ぶのだろうと思っていたけれど、今回、自民党候補に4万5000票もの大差をつけられて敗れた。敗因を自らのせいにせずに、ネットでの誹謗中傷のせいにするなんて、情けなさすぎる。彼を含めてもう戻ってはこれない人が多いと思われる。小選挙区でもこれだけ、新陳代謝が働くことがあるのである。
さて自民党。2年前の総選挙で敗れた元職もいるけれど、新人も100人近くはいるのではないか。なにせ今回全小選挙区に候補を立てて、自民党というだけで当選した人も多いのである(比例復活組も含めるとほとんどが当選しており、完全な落選者は数えるほどしかいない)。以前の小泉チルドレン、安倍チルドレンの時を思い起こし、彼らを教育・監督していかなければならない。かつては派閥がその役割をかなり担っていたが、今派閥は麻生さんの所を除いて消滅してしまった。会社の新人教育のように、一から教えなければならないことが多いと思われる。個々人がやはりそれぞれ能力と適性を持たなければ、政党も弱いものになってしまう。そして、絶対多数にあぐらをかくことなく、どうか謙虚に、国政を進めていってほしいと願っている。